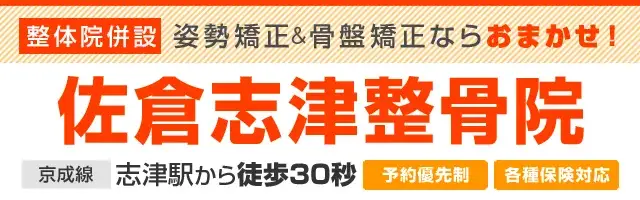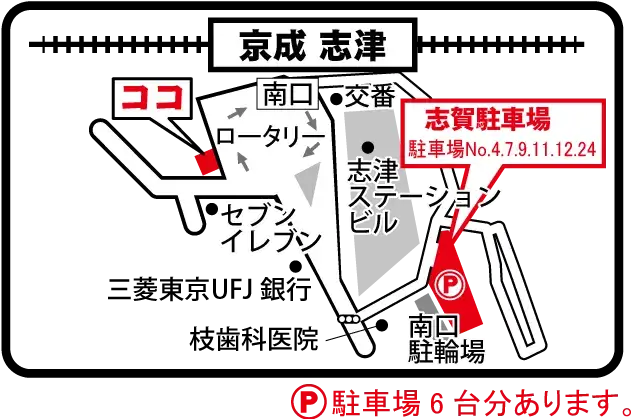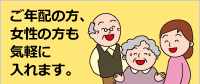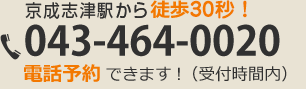身体のゆがみ


こんなお悩みはありませんか?

最近腰が痛くなりやすくなった
肩の左右の高さが違ってきて写真や鏡を見ると左右非対称になった
頚や肩が昔と比べると疲れやすくなった
歩行や膝を曲げるといった日常生活上の動きで、痛みや違和感を感じる
昔と比べると姿勢が悪くなってしまったと感じることが増えた
これらの症状が出ている場合は身体のゆがみからきている場合があるので、詳しく説明していきます。
身体のゆがみについて知っておくべきこと

今回は、身体のゆがみについて知っておくべきポイントを2つの項目に分けてご説明いたします。
まず1点目の項目は、身体にゆがみが生じるとどうなるのかという点についてです。
筋肉の柔軟性が低下し、血流が滞ることで、痛みや違和感が生じやすくなります。
その理由としては、血流の低下によって細胞のエネルギーを生み出す力が弱まり、筋肉や関節の働きがスムーズにいかなくなってしまうためです。
次に2点目の項目は、そのような状態から身体のゆがみがさらに進行してしまった場合に起こりうる症状についてです。
たとえば、朝起きたときに疲れが取れにくいと感じたり、プライベートの場面などでパフォーマンスの質が低下したと感じることがあるかもしれません。
症状の現れ方は?

症状の現れ方には、3段階に分けて進行していくと考えられます。
1段階目は、日常生活における動作や作業の中で、痛みや違和感を感じることが増えてくる段階です。
2段階目は、筋肉の柔軟性の低下や血流の滞りなどにより、身体のこわばりを感じやすくなる段階です。
3段階目は、筋肉や靱帯といった軟部組織の緊張が身体の許容範囲を超えてしまい、その影響が身体の土台である骨格にまで及んでくる段階です。
具体的な例としては、腰の骨や背中の骨の位置関係が、本来あるべき正常な位置からわずかにずれてしまうことが挙げられます。
その他の原因は?

次の項目では、身体のゆがみを引き起こすその他の原因について、2つの項目に分けてご説明いたします。
1点目は、運動不足によって全身の筋肉の柔軟性が低下することが原因と考えられます。
これは前の項目でも触れたとおり、血流の滞りにつながり、身体のゆがみを引き起こす一因となります。
2点目は、現代社会における課題のひとつである、デスクワークやVDT(Visual Display Terminal)作業の増加による影響です。
このような作業が増えることにより、上半身と下半身をつなぐ筋肉や、姿勢を保つための筋肉に負担がかかり、ゆがみを引き起こす可能性があると考えられます。
身体のゆがみを放置するとどうなる?

身体のゆがみを放置した場合にどうなるのかについて、2つの項目に分けてご説明いたします。
1点目は、身体の許容範囲を超えてゆがみが大きくなってしまった場合に起こり得る身体の変化についてです。
まず、血流の滞りによって疲れやすさが現れやすくなります。さらにその状態が続いて限界を超えると、朝すっきりと起きられないといった状態になることがあります。
2点目は、頭痛などの身体的な不調という観点からの内容です。
身体の許容範囲を超えたゆがみがある場合、それが原因となって偏頭痛などの不調が起こりやすくなることが考えられます。
当院の施術方法について

当院では、まずお身体をどの程度まで良い状態に導いていきたいのかというゴールを明確にした上で、施術方法を検討いたします。
つまり、「根本的に身体のゆがみを軽減したいのか」、あるいは「今感じている不調のみを取り除きたいのか」といった目的に応じて施術内容が異なります。
前者の観点から施術方針を考える場合には、矯正施術や鍼施術、筋肉へのアプローチとしてのストレッチや猫背の軽減を目指すメニューなど、複数の選択肢の中から、患者さまの身体の状態と施術者の専門的な視点をすり合わせながら、最も適した内容をご提案し、施術を進めてまいります。
後者の観点から施術方法を検討する場合には、まずは矯正施術を第一の選択肢としてご案内し、現在の症状に対して適切な対応を行ってまいります。
軽減していく上でのポイント

身体のゆがみの軽減を目指すうえでのポイントについてご説明いたします。
施術後の日常生活における注意点を2つの項目に分けてお伝えいたします。
1点目は、デスクワークなどの作業時に気をつけていただきたい点についてです。
長時間の作業によって筋肉の柔軟性が低下し、それが原因となって身体のゆがみを引き起こす可能性があることは、これまでの項目でもご説明してきました。
そのため、適切なタイミングで休憩を取ることが推奨されています。
具体的には、1時間ごとに5分、2~3時間ごとに15分程度の休憩を取ることが望ましいとされています。
2点目は、運動習慣を身につけることが推奨されている点です。
運動を行うことで血流や体内の循環が促され、その副次的な効果として筋肉の柔軟性が保たれやすくなり、身体のバランス維持にもつながるとされています。
監修

佐倉志津整骨院 院長
資格:柔道整復師、高等学校教諭1種免許状(保健体育)
出身地:大阪府茨木市
趣味・特技:音楽、アニメ