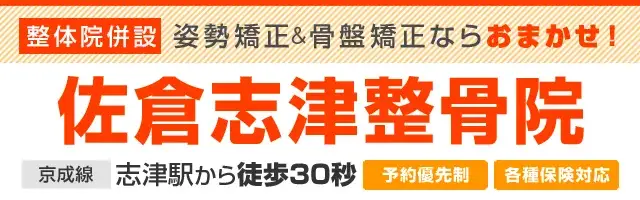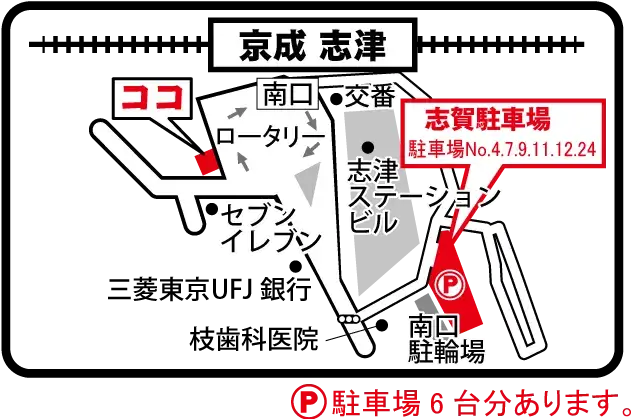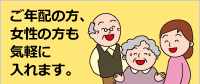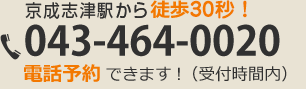巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

最近、リュックを肩の前に掛けようとするとずり落ちてしまい、あまり肩掛けをしなくなった。
昔と比べて、肩の前に硬結(筋肉の繊維が固まり、痛みが出る場所)が現れるようになった。
肩を動かすと痛みを感じるようになった。
肩周りに重だるさやしびれを感じることが増えてきた。
鏡で見ると、左右の肩の位置がずれていて、非対称になっている。
これらの症状がある場合、いわゆる巻き肩の症状が出ている可能性が高いです。
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩について知っておくべきことを、今回は大きく二つの項目に分けてご説明いたします。
まず一つ目の項目は、「巻き肩が起きやすい人」についてです。
肩甲骨まわりの軟部組織(筋肉や靱帯)に繰り返し負担がかかる動作をしている方、長時間のデスクワークを行っている方、または怪我や神経麻痺などの後遺症によって肩の可動域が制限されている方は、その影響で巻き肩へと移行してしまう可能性があります。
次に二つ目の項目は、「正常な状態と巻き肩の状態における位置関係」についてです。
肩は肩甲骨と上腕骨で構成されており、肩甲骨の外端部分は肩峰と呼ばれ、体表から観察することが可能です。正常な場合、肩峰と耳の位置が同一線上にありますが、これが前方へ変位している場合には、巻き肩の状態であると判断されることがあります。
症状の現れ方は?

症状の現れ方についてご説明いたします。
いくつかの要因が考えられますが、大きく二つの項目に分けてご紹介いたします。
一つ目は、肩甲骨や肩まわりに痛みや違和感を感じ始めることです。
この原因として考えられるのが、筋肉の緊張によるものです。正常な筋肉の状態であればスムーズに動作しますが、緊張があると動きに制限が出て、それが痛みの要因となることがあります。
二つ目は、姿勢の問題につながるケースです。
巻き肩になると左右の肩の位置が正常な位置からずれてしまうため、服を着たときや写真撮影の際などに違和感を覚え、巻き肩を自覚する場合があります。
その他の原因は?

その他の原因として考えられる項目についてご説明いたします。
複数の要因が考えられますが、ここでは二つの項目に分けてご紹介いたします。
一つ目として考えられるのは、肩の周辺に付着する筋肉や靱帯など、構成している軟部組織の緊張が正常な状態を超えてしまうことで、それが原因となり巻き肩を引き起こす場合があるということです。肩まわりに付着する代表的な筋肉としては、三角筋や前鋸筋などが挙げられます。
二つ目は、現代の生活において欠かすことのできないデスクワーク作業の増加です。一つ目の項目でご説明した筋肉の緊張がより強くなり、それによって巻き肩の状態が進行し、症状が悪化してしまう可能性があります。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置しておくとどうなるのかについてご説明いたします。
大きく二つの項目に分けて、それぞれの内容をご紹介いたします。
一つ目は、神経に影響を及ぼし、しびれや痛みといった症状が現れる可能性があるという点です。代表的なものとしては「胸郭出口症候群」や、パソコン作業の増加による「VDT障害(Visual Display Terminal障害)」などが挙げられます。これらの症状が一度発生してしまうと、症状の軽減には時間を要する場合があります。
二つ目は、不良姿勢が原因となり、日常生活における支障や作業効率の低下につながる可能性があるという点です。具体例としては、タイピング作業の効率が落ちたり、棚の上から物を取ろうとした際に肩の痛みを感じたりする場合があるとされています。
当院の施術方法について

施術の方法についてご説明いたします。
まず一つ目の項目は、巻き肩を引き起こしている筋肉に対するアプローチです。筋肉の柔軟性を高めることを目的として、当院では上半身ストレッチや肩甲骨はがし、鍼施術などを行うことが選択肢として考えられます。上半身の筋肉の状態が整ってきたら、次の段階へと進んでいきます。
二つ目の項目は、姿勢や骨格に対するアプローチです。一つ目でご説明した筋肉に対する施術と並行して、巻き肩の症状の軽減が期待できるよう取り組んでまいります。
そのために、当院では猫背軽減メニューや骨格矯正といったメニューをご用意しており、症状に合わせた施術を行うことが可能です。
軽減していく上でのポイント

症状の軽減を目指すためのポイントについてご説明いたします。
この項目では、大きく二つの内容に分けてご紹介いたします。
一つ目の項目は、施術の頻度や期間についてです。
症状が現れている年齢層によって、施術の期間には違いが生じます。一般的には、年齢が若いほど施術の期間は短く、症状の変化も早く実感されやすい傾向があります。
二つ目の項目は、日常生活の中で気をつけるべき点についてです。
巻き肩を強めてしまう要因としては、不良姿勢が関係していることが多く見受けられます。そのため、日常生活において姿勢に注意を払うことが大切です。具体的には、長時間にわたるパソコン作業やスマートフォンの使用などが要因として想定されています。
監修

佐倉志津整骨院 院長
資格:柔道整復師、高等学校教諭1種免許状(保健体育)
出身地:大阪府茨木市
趣味・特技:音楽、アニメ